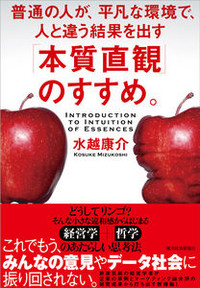(株)トークアイ代表取締役CEO 佐野良太 × 首都大学東京准教授 水越康介氏
メタファーを媒介した「対話」
佐野:次に、メタファーの役割ですが、「もうメタファーはメタファーでしかない」と書かれています。観察の理論負荷性の話も関係するのかと思いますが、具体的にどうすればいいのか何か提案はありますか?
水越:繰り返しになりますが、それは「対話だ」と言うしかない。メタファーを媒介して会話する。それが何かについてお互いに考えてみる、話してみることです。
佐野:それは別にメタファーでなくてもいいのかもしれないですね。
水越:いいと思います。あともう一つ、その章の頭で書いたのですが、この手の方法というのは、結構臨床の手法に取り入れられていると思います。カウンセリングに近いと思うのですが、何かするわけではないのだけれども、とにかくひたすら一緒にいてあげるのです。そうすると直接的な問題としてずっと一緒にいるので、何かそこで無意識のうちに思うところとか感じるところができ上がっていって、あるとき何かの了解が生まれる。そういうときを臨床では待つのだと思いますが、それも一つの方法かなと思います。
佐野:ロールシャッハテストで使われるような無意味図形を見てもそこに共通に何か生み出せるものがあるとすると、必ずしも構成されたメタファーだけがその可能性を生み出すものではなくて、相互作用を生み出す媒体は他にもあるような気がします。
 水越:例としてはどうかという気はしますが、それを書いていて何となく感覚として思っていたのは、いわゆる「飲みニケーション」も悪くはないのかなと。お互いに了解し合うような無意識の状態を何らか相互作用するようなタイミングとしてはありかなという気はします。「それでは飲みに行こう」という話だと、あまり理論的ではないのですが(笑)。
水越:例としてはどうかという気はしますが、それを書いていて何となく感覚として思っていたのは、いわゆる「飲みニケーション」も悪くはないのかなと。お互いに了解し合うような無意識の状態を何らか相互作用するようなタイミングとしてはありかなという気はします。「それでは飲みに行こう」という話だと、あまり理論的ではないのですが(笑)。
当事者の立場でお客さんの経験を理解する
佐野:「実在論的、現象学的視点に基づくインタビュー」という箇所で、「事前に仮説を持ち、それを第三者的な立場で検証するのではなく、当事者の立場で被験者の経験を理解する」と。それで生活世界の記述が大事だと書かれています。事前に仮説を持って、それを第三者的な立場で検証することが、今までのマーケティングリサーチの立場で、当事者の立場で被験者の生活世界を記述すると言うと、「おまえの意見は聞いていないぞ」という話になってしまいがちです。この対立については、どういう理屈で後者のほうがこれからは大事だと言えるのでしょうか。
水越:同じことの繰り返しになりますが、前者のほうは証明のしようがない、どんなにやっても数の問題ではなく、そもそも相手の心があるかどうかはわからない。その最初の出発点の問題で本来行き詰まっているはずで、あまり効率がよくないし、効果的でもないということです。それではどうするのかというと、お客さんに経験を語ってもらう。彼、彼女がそれを買った状況とか、そのとき何を考えていたのかということをまずはきれいにできるだけ丁寧に記述する。そこから何を引っ張り出せるか、それが何なのかということはもっぱら調べた側の問題で、それを材料にしてこっちで考えればいいことですよね。こっちで考えたことは自分たちで考えたことなのだから、間違っているとか正しいとか言いようがない。そう思ったのだからそれしかない、というのが後者の立場です。
佐野:そのあたりの納得感が旧パラダイム側と新しいパラダイム側によって全く異なりますね。旧側に属する方にとってはなかなか受け入れ難い話なのかなと思います。
水越:そうですね。
自然科学の方法を社会科学に応用できるか
佐野:次に、論理実証主義と合理的批判主義の話が出てきます。我々は帰納法の世界に慣れていて、ある意味所与に正しいと考えていますが、論理的に考えると必ずしもそれは成り立たないと書かれています。
水越:もともと科学哲学の領域で100年ぐらい前に議論された話です。論理実証主義を標榜したウィーン学団が有名ですが、彼らが自然科学の方法を社会科学に応用できるじゃないか、全部それでいけるはずだと主張したわけです。
佐野:「語りえないものについては沈黙せねばならない」ですね。
水越:彼らの主張は社会科学でも自然科学と一緒で、モノを確定できて、モノを数えればそれをベースにして理論をつくれるのではないかというものでした。しかし、途中でこれは難しいのではないかと、段々と議論が後退していきます。当時は非常にシンプルな話で、統計的な知識もあまりなかったので、何個集まってもそれが無限にそうであるということは証明できないと分かってしまった。それに対して、ポパーが無限を証明することはできないけど反証はできるじゃないか、反証は1個あればいいのだからという議論で立て直しを図りますが、結局それもあまりうまくいかない。理論負荷性の関係で、この1個が反証になっているかどうかというのはやはり無限の問題をはらむから証明できないわけです。
佐野:カラスは黒いという命題を証明するためには片っ端からカラスを捕まえてきて、それが黒であるということを確かめ続ければ、たぶんカラスは黒いのだろうといえる。ところがある日突然白いカラスを捕まえたら、カラスは黒いという命題は否定されたと考えるわけです。それでも、その白いカラスというのははたしてカラスなのだろうか?という疑問が次に出てきて、白いカラスはカラスではないと言ってしまえば、最初の命題はまだ正しいわけです。しかしそうするとカラスの定義自体のトートロジーになってしまって、カラスは黒いと定義したものについて、もはや論証する必要はないということになってしまうということですよね。
水越:本来であれば最初の「カラス」の定義の中に黒色だとか、鳥であるということが含まれていますので、それを証明するということが変な話です。
リサーチすることで社会が変わる?
佐野:「リサーチと社会の相互依存的で再帰的な関係を問題にするリサーチャーの内部性と行為と規範の分離困難性を問題にする懐疑論的関係」という栗木先生のお話は非常に難解なので、わかりやすく解説していただきたいのですが。
水越:前半は預言の自己成就みたいなイメージです。リサーチすることで社会や、お客さんの気持ちが変わってしまうとすると、当のお客さんのその気持ち自体を調べようがないという再帰的な関係です。
佐野:そのリサーチすることによってその人の精神状態が変わってしまうということですか。
水越:たしかそうだったような気がします。
佐野:それでは「行為と規範の分離困難性を問題にする懐疑論的関係」というのは、どういう意味なのでしょう。
水越:自分がある行為をするときにそれがどういうルールに従っているかと言うことと、なぜ自分がそれをしているのかというのは明確にはこう分けて考えられないという意味です。
佐野:自分がやっていることと、それを行わせている規範というものを分離して考えることはできないということですか。
水越:そうです。
行為と規範は現実には分けられない状態で進んでいる
佐野:例えば将棋の話で言うと、やりながらルールが変わってしまうということは、何を意味しているのでしょうか。
水越:はた目から見れば、将棋から「ピン消し」になったようにみえる。このとき、要するにルールが変わったと言うのですが、多分それは外から見ているからそう見えるだけで、当事者の中では首尾一貫しているということです。遊んでいるという行為があって、それが延々と続いている行為とルールというのが分離せずにつながっていて、途中で負けそうになったから何かちょっとこうやってとか、こんな感じにしてとか、勝手に条件をつけて、いや、子供は何か有利にゲームしてもいいとか、そんなルールをつけ足しながら変えていくわけです。本来は連続して行為とルールというのがくっつきながら動いているものを、後から見ると、あるとき将棋をやっていたものがケンカして「ピン消し」になったと理解できてしまうわけですね。
佐野:行為とルールが相互作用しているというか、そもそも分離不可能なものだと。
水越:現実には分離不可能だと思います。論理的な話だと、クリプキがプラスとクワスという話をしています。5足す(プラス)7はと言ったときに12になるじゃないですか。そのときには、プラスというルールがあるわけです、足し合わせるという。しかし、あるとき5足す8は3ですと言われる、このときに僕たちは、おかしくない?13じゃないのという話になるわけです。しかしながら、やっている人は幾らでも説明ができて、合計点が12を超えたらそれはもうゼロにしてしまって数え直すのだというルールを足せば、5足す8は3でオーケーになる。これを仮にクワスという新しい式だと呼んだとすると、最初の人がプラスに従って12まで計算していたのか、それともクワスに従って5足す7を12と計算していたのかということは判定しようがないわけです。我々は、足し上げるという行為は、事前に明確なルールがあって、行為が合っているかどうかはルールで判定できると信じているわけですが、実はそんなにうまく判定のしようがない。あるときは変なルールが出てきうるという状態を含んでいます。そういう意味で行為とルールというのは現実には分けられない状態で進んでいます。あるときこれはおかしくない?と言われたときに初めて、ああ、プラスルールというのと特殊なクワスルールというのがあるのだなというのを遡及的に判定できる。
佐野:日本人はどちらかというとルールというのは永久に変わらないというイメージというか意識が根底にあるような気がします。そういう意味で言うとルールも変わり得るということとか、見えないルールもあるとか、そういうのだってなかなか理解し難いところがありますね。例えば大リーグでは点差が開いているときに盗塁すると。
水越:怒られる。
佐野:そういう、明文化というか明確化されているわけではない、あいまいさみたいなものというのは、現代日本人には受け入れられにくいのかなと思います。
水越:確かにそうですね。その明文化して行為と規範をきれいに分けておければ通常の自然科学的なリサーチが生きるのですが、現実には行為と規範がくっついているのだとすると、これがこういうルールに従って彼は動いているのだとかいう説明の仕方自体が意味を持たないことになって調査がうまくできなくなる。別の方法が必要だよねと言う、そんなストーリーだったと思います。
水越 康介(みずこし こうすけ)
1978年生まれ。神戸大学大学院経営学研究科博士後期課程修了。現在、首都大学東京
大学院ビジネススクール准教授。博士(商学)。専攻は市場戦略論(マーケティング論)、
商業論、消費者行動論。
Webサイト:水越康介私的市場戦略研究室 https://www.mizkos.jp
水越先生との対談記事総集編(脚注、図表付き)をPDFファイル形式でダウンロードすることができます。
ダウンロードページのフォームから所定事項を送信の上、ダウンロードしてください。